診療時間
5Fで診療を行っております。
| 診療 時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:30 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~ 18:00 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
※最終受付(午前・午後)診療時間終了の30分前
休診日…日曜午後
当院の内科について
何となく身体の不調を感じる、どこに相談したらいいかわからないなどでお困りの患者様にとって、信頼されるようなかかりつけ医を目指しています。
内科診療の風邪・生活習慣病の他に、呼吸器・消化器・循環器・血液・内分泌・感染症・アレルギーなども診察しています。内科で気になる所見がありましたら、各疾患の専門医師にご紹介させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
※当院では百日咳の検査・診断ができる体制です。
内科で対応する症状
- 咳
- 痰
- 鼻づまり
- 頭痛
- 吐き気
- 嘔吐
- 腹痛
- 便秘
- 下痢
- むくみ
- 黄疸
- 息切れ
- 動悸
など
内科で対応する病気
高血圧
高血圧とは、血圧が正常より高い状態を指します。緊張やストレスなどで血圧は変動しやすいですが、診察室での測定で140/90mmHg以上、家庭での測定で135/85mmHg以上が高血圧とされます。
高血圧の状態が長期間続くと、動脈硬化が進み、脳梗塞や脳卒中、心筋梗塞、狭心症、腎臓病などのリスクが高まります。また、心臓の機能が低下して心不全を引き起こす可能性もありますので注意が必要です。
治療は、まず食生活の見直しや減塩、適度な運動による減量など、生活習慣の改善を行います。それでも血圧が下がらない場合には、薬物療法を検討します。適切な治療を続けながら、血圧を正常値に保つことを心がけましょう。
糖尿病
糖尿病は、血液中の血糖値が長期間高い状態が続く病気です。これは、血糖値を調整するインスリンの分泌量が減ったり、インスリンが正常に働かなくなったりすることで起こります。
糖尿病は初期症状がほとんどないため、自覚しないまま進行してしまうことがあります。しかし、適切な治療をしないと血管が傷つき、血流が悪くなります。その結果、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害といった合併症だけでなく、脳卒中や心筋梗塞のリスクも高まります。さらに進行すると、失明、足の切断、人工透析が必要になることもあり、日常生活に深刻な影響を与えます。
当院では、糖尿病専門医が詳しい検査と適切な治療を行っています。血糖値に異常が見られた場合は、ぜひお早めにご相談ください。
脂質異常症
脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪の数値が高すぎたり、低すぎたりする状態を指します。この状態が続くと、自覚症状がないまま動脈硬化が進み、血管が狭くなったり詰まったりすることで、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすリスクが高まります。
主な原因は、不規則な生活習慣である過食、過度の飲酒、喫煙、運動不足などです。そのため、栄養バランスのとれた食事や禁酒、運動を取り入れるといった生活習慣の改善が大切です。また、早期発見のために定期的な検査を受けることをお勧めします。
高尿酸血症
尿酸が過剰になると、体内で結晶ができて足の親指の付け根に溜まり、痛風を発症します。尿酸は水に溶けにくく、血液中では尿酸塩として存在し、血中の尿酸値が通常よりも高い状態になります。激痛・腫れ・発赤などが起こり、腎臓に結晶ができると腎臓結石となります。尿酸値が高くなる原因に、プリン体の大量摂取があります。ビール・レバー・魚卵・鰯・海老・鰹・干し椎茸などの食品にプリン体は多く含まれるため、これらの食品によるプリン体の大量摂取は注意が必要です。治療には生活習慣の改善と薬物療法を行います。食習慣の見直し、カロリー制限と適度な運動で減量に努めます。肥満、痛風関節炎などを防止するため、必要と判断されれば非ステロイド抗炎症薬を用います。
花粉症
花粉症とは、春や秋などの花粉が飛散する時期に起きます。春にはスギやヒノキ、秋にはブタクサなどのアレルゲンが飛散します。鼻水・充血・流涙・皮膚の掻痒感・倦怠感・微熱・不眠などの症状が起き、悪化すると日常生活に支障を来たすほど辛い症状が起きます。当院では、アレルギー検査を行っています。花粉が飛散する時期にアレルギー症状で辛い思いをせずに花粉の飛散時期までに適切な治療を開始することをお勧めします。
気管支喘息
喘息は、空気の通り道である気管支が炎症を繰り返すことで、過敏になった状態です。過敏になると、少しの刺激でも気道が狭くなり、激しい咳、呼吸困難、ヒューヒュー・ゼイゼイという喘鳴など特徴的な症状があらわれます。これを喘息発作といいます。
喘息は小児に多い疾患で、その場合多くはアレルギーが原因となっています。
成人の場合は、アレルギーの他にも過労や化学的刺激、ストレスなど心因的な要素、気候などの環境的要因などが原因として考えられます。
まずは、原因をつきとめ、発作を起こりにくくすることが大切です。
インフルエンザ
インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症です。インフルエンザウイルスにはいくつかの型がありますが、そのうち人に感染するものはA、B、Cの3種類で、毎年異なる型のウイルスが流行します。流行は11月の終わりごろから始まり、1月をピークに3月ごろまで続きます。
インフルエンザは咳、鼻水、のどの痛みといった風邪のような症状を呈することもありますが、それに加えて、38℃以上の高熱、頭痛、倦怠感、筋肉や関節の痛みといった全身症状が強くあらわれる傾向があります。感染してからの潜伏期間は1~3日程度で、通常1週間ほど症状が続きだんだんと治まっていきます。
感染力が強く爆発的に感染を広めていくことがありますので、症状を感じたら早めに受診することをお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群
眠っている最中に、呼吸が停止する、または呼吸が弱くなる、いびきをかくといった状態がある場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。睡眠の質が低下するため日中の生活に影響があります。また、血管や心臓などにも負担がかかり、最悪の場合突然死にも繋がる可能性があります。睡眠時無呼吸症候群によって高血圧や糖尿病などの発症リスクが高まることもわかっています。睡眠時のことで、自覚しづらい疾患ですが、何かしら徴候があれば、早めにご相談ください。
担当医師
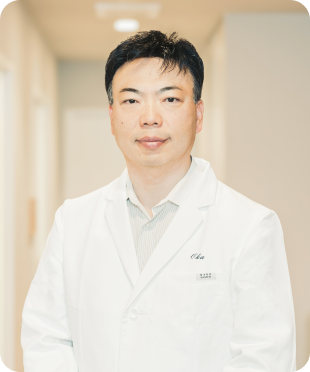
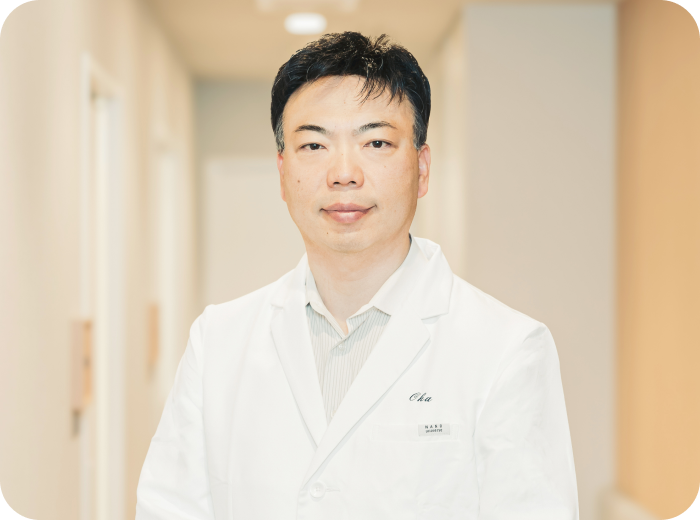
内科岡 秀昭Oka Hideaki
経 歴
| 2000年 | 日本大学医学部 卒業 |
|---|---|
| 2009年 | 横浜市立大学大学院 卒業 |
| 2009年 | 医学博士 取得 |
| ~2016年 | 神戸大学病院感染症内科を経て、関東労災病院や東京高橋病院などで感染症診療部門を歴任 |
| 2017年 | 埼玉医科大学総合医療センター 総合診療内科・感染症科 (診療部長:准教授として赴任) |
| 2020年 | 7月より同教授、9月より病院長補佐 |
資格・
所属学会
- 横浜市立大学呼吸器病学 客員教授
- 日本感染症学会專門医、指導医、評議具
- 日本呼吸器学会専門医
- 日本内科学会総合内科専門医・指導医
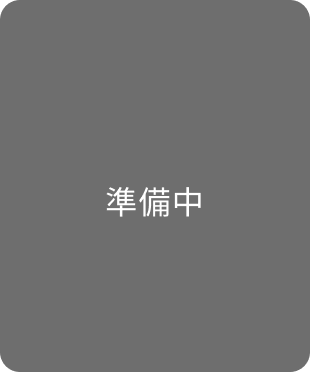
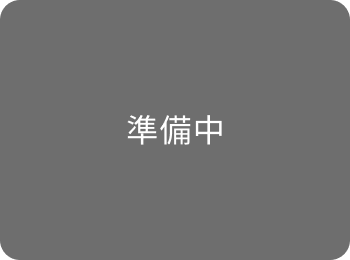
内科塚田 訓久Tukada Kunihisa
経 歴
| 1991年 | ラ・サール高校卒業 |
|---|---|
| 1997年 | 東京大学医学部医学科卒業 |
| 2001年 | 東京大学感染症内科 |
| 2006年 | 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター |
| 2010年 | 同 医療情報室長 |
| 2019年 | 同 専門外来医長 |
| 2022年 | 国立病院機構東埼玉病院 臨床研究部長 |
| 2024年 | 埼玉医科大学総合医療センター 感染症科・感染制御科 教授 |
資格・
所属学会
- 日本内科学会 総合内科専門医・指導医
- 日本感染症学会 感染症専門医・指導医
- 日本エイズ学会 指導医
- 日本病院総合診療医学会 認定病院総合診療医
- 労働衛生コンサルタント(保健衛生)
- 公認心理師


内科城川 泰司郎Shirokawa Taijiro
経 歴
| 2008年 |
東海大学病院 臨床研修プログラム |
|---|---|
| 2011年 | 筑波大学病院 総合診療科 病院総合医コース |
| 2013年 |
水戸協同病院 総合診療科 |
| 2015年 |
水戸協同病院 感染症科 |
| 2016年 |
東京医科大学病院 臨床検査医学科 |
| 2018年 |
千葉大学医学部付属病院 総合診療科 |
| 2020年 |
昭和大学病院 膠原病内科 |
| 2021年 |
関東労災病院 感染症内科 |
| 2023年 |
医療法人社団WHMクリニックプラス高円寺 |
| 2025年 |
西荻窪駅前クリニック |







