ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)とは
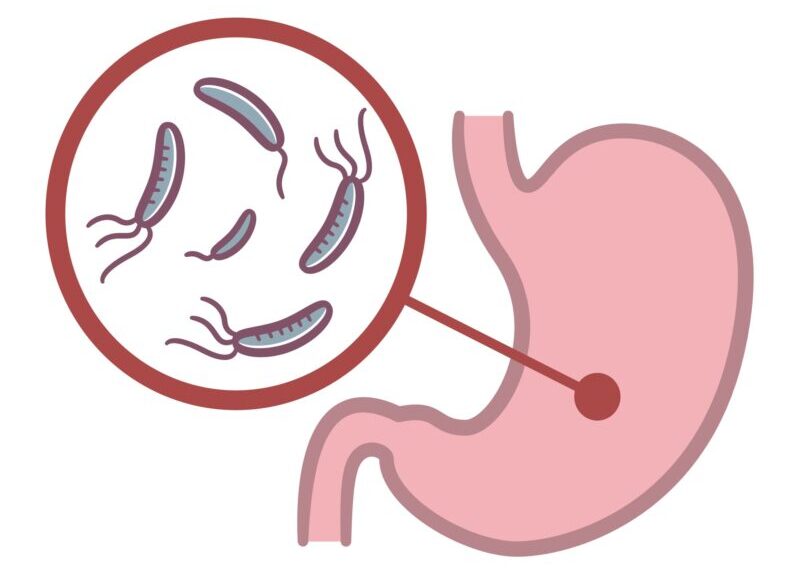 ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)とは、胃粘膜に生息することができる細菌です。本来、強酸性である胃の中は細菌が生息できる環境ではありませんが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を分泌して自身の周囲の酸を中和することで生息を可能にしています。
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)とは、胃粘膜に生息することができる細菌です。本来、強酸性である胃の中は細菌が生息できる環境ではありませんが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を分泌して自身の周囲の酸を中和することで生息を可能にしています。
ピロリ菌が胃に生息し続けると、胃や十二指腸に炎症を引き起こし、胃がんや大腸がんなど重篤な病気を引き起こす恐れがあるため、注意が必要です。
ピロリ菌の主な感染経路は不衛生な井戸水などで、主に発展途上国などで多くの感染例が見られますが、日本も先進国の中では最も感染率の高い国となっています。日本の場合は飲み水からではなく、家族間の口移しなどによる感染拡大が多く報告されています。そのため、血縁者に胃がんや胃潰瘍、大腸がん、十二指腸潰瘍の罹患者がいる場合には、ご自身もピロリ菌に感染している可能性があるため、一度検査で確認しておいた方が良いでしょう。
検査によって陽性判定が出た場合は、抗生物質と制酸剤による除菌治療を実施します。除菌治療を行なっておくことで、ご自身だけでなく周囲の方に対しても多くの重篤な病気の発症リスクを低下させることができます。
ピロリ菌感染検査
ピロリ菌の検査は、胃カメラ検査とその他の検査に大別されます。
胃カメラ検査は、検査の際に胃粘膜の組織を採取して下記のような様々な病理検査にかけることで感染の有無を確認することができます。
なお、胃カメラ検査以外にも検査の方法はありますが、ピロリ菌の除菌治療に保険を適用させるためには、胃カメラ検査を実施しておくことが必須条件となります。
胃カメラで
組織採取をして行う検査
迅速ウレアーゼ試験
迅速ウレアーゼ試験は、採取した組織にウレアーゼが含まれているかどうかを調べる検査で、即座に検査結果を知ることができます。
ピロリ菌は胃の中に生息するために、ウレアーゼを分泌します。そのため、この酵素が確認されればピロリ菌感染は陽性となります。
鏡検法
鏡検法とは、採取した組織を染色して顕微鏡で詳細に観察する検査です。
培養法
培養法とは、採取した組織を人工的に培養してピロリ菌が増殖するかどうかを調べる検査です。
胃カメラ検査なしで行う検査
尿素呼気試験
尿素呼気試験とは、検査薬服用前の呼気と服用後の呼気を比較することでピロリ菌感染の有無を確認する検査です。
比較的簡単に行える上、検査精度も高いことから、ピロリ菌の除菌治療を行った後の確認にも広く実施されている検査です。
抗体検査
抗体検査とは、血液や尿の中にピロリ菌に対する抗体が含まれているかどうかを確認する検査です。
抗体が確認されれば、ピロリ菌陽性となります。
便中抗原検査
便中抗原検査とは、便の中にピロリ菌の抗原が含まれているかどうかを確認する検査です。
抗体が確認されれば、ピロリ菌陽性となります。
ピロリ菌によって
発症リスクが上昇する
病気
ピロリ菌は強酸性の胃の中に留まるためにウレアーゼを分泌しています。このウレアーゼが尿素を分解してアンモニアが生成され、このアンモニアが胃粘膜や十二指腸粘膜を損傷することで炎症を引き起こし、様々な病気へと繋がります。
炎症が長期間継続すると、炎症部に潰瘍が形成されて胃潰瘍を引き起こしたり、胃粘膜が萎縮して胃がんを引き起こす恐れもあるため、注意が必要です。
従って、これら重篤な病気を予防するにはピロリ菌除菌治療を行うことが最も効果的です。
ピロリ菌の除菌に成功すれば、炎症や潰瘍を改善・予防することが可能となり、胃潰瘍や胃がんなどの発症リスクを低下させることができます。ただし、除菌に成功したとしても胃がんの発症リスクはゼロにはなりませんので、その後も定期的に検査を行って自身の状態を把握しておくことが大切です。
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 機能性ディスペプシア
- 胃がん
- 慢性蕁麻疹
- 胃ポリープ
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 胃MALTリンパ腫
など
ピロリ菌と胃がん
ピロリ菌が胃に長期間留まり続けると、胃粘膜に慢性的な炎症を引き起こして次第に胃が萎縮し、胃がんの発症リスクを高めます。
そのため、ピロリ菌感染が確認された際には確実に除菌治療を行なっておくことが、将来的な胃がんの予防に効果的です。
しかし、除菌治療に成功した場合でも胃がんを発症することもあるため、除菌後も定期的に検査を行なって自身の胃の状態を把握しておくことが大切です。
なお、検査では胃カメラ検査が最も有効です。胃カメラ検査では、細径の内視鏡スコープを使用して胃粘膜の状態を直接確認することができるため、見逃されがちな微細な病変も逃さず発見することができ、胃がんの早期発見に役立ちます。
胃がんリスク検診
現在、胃がんリスク検診では血液を採取するスクリーニング検査が広く普及しております。
これは、採取した血液からピロリ菌の抗体の有無を調べることができるほか、ペプシノーゲンの値を測定することで胃粘膜の炎症や萎縮の程度を確認できるため、総合的に胃がんの発症リスクを判断することが可能です。
胃がんリスク検診によって胃がんの可能性が疑われた場合には、胃カメラ検査を実施してさらに詳しい状態を確認する必要があります。
除菌治療
ピロリ菌の除菌治療では、まずは2種類の抗生物質と胃酸分泌抑制剤を1週間服用し、約1ヶ月後に除菌が成功したかどうかを確認するための判定検査を実施します。なお、1回目の除菌治療による除菌成功率は90%と報告されています。
1回目の治療で除菌に失敗した場合には、1回目で使用した2種類の抗生物質のうち1種類を他のものに変更し、2回目の除菌治療を実施します。なお、1回目と2回目を合算した除菌成功率は99%と報告されておりますので、2回実施すればほとんどの場合は除菌に成功します。
なお、ピロリ菌検査の際に胃カメラ検査を行った場合は、ピロリ菌除菌治療は2回目まで保険適用となります。3回目以降も除菌治療を行うことは可能ですが、その場合は自費診療となります。
治療の副作用について
ピロリ菌除菌治療を行うと、下痢や軟便、嘔気、味覚障害などの副作用が現れることがありますが、これら副作用は服用後しばらくするとほとんどの場合は自然治癒します。また、除菌効果が現れると一時的に胸焼けなどの症状が現れることもありますが、こちらもしばらくするとほとんどの場合は自然治癒します。
万が一、このような副作用の症状が長引いたり、激しい症状が現れた場合は、できるだけ早く当院にご相談ください。







